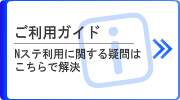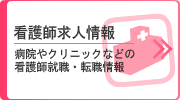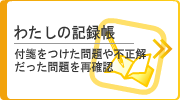第103回国家試験必修問題解説(午前問題1〜25)
【問題1】 日本の平成23年(2011年)における出生数に最も近いのはどれか。
正解 2
- 55万人
- 105万人
- 平成23年人口動態統計の概況によると、平成23年の出生数は105万806人で、前年の107万1304人より2万498人減少し、出生率(人口千対)は8.3で前年の8.5を下回った。合計特殊出生率は1.39で前年と同率となっている。
- 155万人
- 205万人
【問題2】 平均寿命は[ ]歳の平均余命である。[ ]に入るのはどれか。
正解 1
- 0
- 平均余命とは、その年齢の人が平均してあと何年生きられるかという統計値であり、0歳の平均余命のことを平均寿命という。
- 5
- 10
- 20
【問題3】 労働基準法で原則として定められている休憩時間を除く1週間の労働時間はどれか。
正解 2
- 30時間を超えない。
- 40時間を超えない。
- 「使用者は原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」と定められている。
- 50時間を超えない。
- 60時間を超えない。
正解 4
- 予防接種
- 正常な分娩
- 人間ドック
- 入院時の食事
- 国民医療費とは、当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したものであり、医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費などが含まれる。正常な妊娠や分娩、予防接種、健康診断、人間ドック、室料差額などは含まれない。
【問題5】 全ての人が差別されることなく同じように生活できるという考え方を示しているのはどれか。
正解 2
- ヘルスプロモーション
- ヘルスプロモーションとは、WHO(世界保健機関)が1986年のオタワ憲章において提唱したもので、人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセスをいう。
- ノーマライゼーション
- 「障害者や高齢者を特別視せず、可能な限り通常の市民生活を送ることができるようにする」という理念やそれに基づく政策をノーマライゼーションという。
- プライマリヘルスケア
- プライマリヘルスケアは、1978年にWHOが採択したアルマ・アタ宣言によって初めて定義づけられた。健康であることを基本的な人権として認め、全ての人が健康になること、そのために地域住民を主体とし、人々の最も重要なニーズに応え、問題を住民自らの力で総合的かつ平等に解決していくアプローチをいう。
- エンパワメント
- エンパワメントとは、個人が内発的な動機を高め、自分自身の力で問題や課題を解決していくことができる社会的技術や能力を獲得すること、または、そのために第三者が環境の整備や必要な資源の提供等の支援を行うことをいう。
【問題6】 出生時からみられ、生後3ヶ月ころに消失する反射はどれか。
正解 3
- 足踏み反射
- 足踏み反射とは、脇の下を支えて足底を床面につけると、下肢を交互に踏み出して歩行しているような動作を見せる反射で、自動歩行ともいう。生後1〜2か月頃に消失する。
- パラシュート反射
- パラシュート反射とは、上体が傾いたときなどに手を広げて上肢を伸ばし、身体を支えようとする反射である。生後7〜9か月頃から出現し、一生消失しない。
- Moro(モロー)反射
- モロー反射とは、頭部を持ち上げて急に落とす動作をした際に、上肢を広げて抱きつくような動きを見せる反射である。大きな音などでも誘発される。生後3〜4か月頃に消失する。
- Babinski(バビンスキー)反射
- バビンスキー反射とは、足底外縁をこすると、母指が背屈し、他の四指が扇状に開く反射である。生後1〜2歳頃に消失する。
正解 1
- 卵胞ホルモン
- 卵巣機能低下によってエストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌は低下する。また、下垂体からの黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌は増加する。
- 黄体形成ホルモン(LH)
- 卵胞刺激ホルモン(FSH)
- 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)
正解 4
- 廃棄物の処理
- 人口動態統計調査
- 看護師免許申請の受理
- 地域住民の健康づくり
- 市町村保健センターは、健康相談や保健指導など、地域住民に密着した対人保健サービスを行っている。地域における母子保健・老人保健の拠点である。
正解 2
- 責任の追及
- 再発の防止
- インシデントレポートの最大の目的は、事故の予防である。個人の責任を追及するのではなく、事故の把握、原因の分析、組織での共有を行い、事故の予防・再発の防止に役立てる。
- 懲罰の決定
- 相手への謝罪
正解 3
- 100ml以下
- 1日の尿量が100ml以下の場合を無尿という。
- 200ml〜400ml
- 1日の尿量が400ml以下の場合を乏尿という。
- 1,000ml〜1,500ml
- 成人の1日の平均尿量は、約1,000ml〜1,500mlである。
- 3,000ml以上
- 1日の尿量が3,000ml以上の場合は多尿である。
【問題11】 普通の呼びかけで容易に開眼する場合、ジャパン・コーマ・スケール
正解 2
- I-3
- 覚醒しているが、自分の名前・生年月日が言えない場合である。
- II-10
- 普通の呼びかけで容易に開眼する場合である。
- II-30
- 痛み刺激を加え、呼びかけを続けると辛うじて開眼する場合である。
- III-100
- 痛み刺激に対して、払いのけるような動作をする場合である。
正解 4
- 歯
- 毛髪
- 爪床
- 眼球結膜
- ビリルビンは弾性線維との親和性が高いため、皮膚、強膜、血管といった弾性線維が豊富な組織に沈着する。特に強膜との親和性が高いため、眼球結膜を観察することで黄疸を確認できる。
正解 1
- 脱水
- 大量の水分が失われるため、脱水が起こりやすい。また、頻回の嘔吐では、胃液の喪失により代謝性アルカローシスがみられることがある。
- 貧血
- 発熱
- 血尿
【問題14】 2型糖尿病の食事療法における1日のエネルギ一摂取量の算出に必要なのはどれか。
正解 3
- 体温
- 腹囲
- 標準体重
- 1日のエネルギ一摂取量は、標準体重(kg)×身体活動量(kcal/kg)によって算出する。なお、標準体重は、身長(m)×身長(m)×22によって算出する。
- 体表面積
正解 3
- ヘパリン
- ヘパリンには、血液凝固阻止作用がある。
- アルブミン
- アルブミンには、膠質浸透圧の維持や薬剤など様々な物質と結合し運搬する作用がある。
- アスピリン
- アスピリンは、シクロオキシゲナーゼの活性を阻害することで、トロンボキサンやプロスタグランジンの産生を抑制し、抗血小板作用と抗炎症作用を示す。
- ワルファリン
- ワルファリンには、抗凝血作用がある。肝臓でのビタミンK依存性凝固因子の産生を抑制し、血栓の形成を防止する。
正解 3
- 32〜33℃
- 36〜37℃
- 40〜41℃
- 腸管を軽度に刺激して適度に蠕動運動を促すよう、浣腸液の温度は、直腸温よりもやや高めの40℃程度とする。温度が低いと、末梢血管が収縮し、血圧の上昇や寒気を起こす。
- 44〜45℃
【問題17】 水平移動時の移送方法の写真を示す。適切なのはどれか。
正解 3



- ストレッチャー接触の予防、患者の容態確認、患者の不安軽減が重要となる。ストレッチャーの前後に一人ずつ配置し、前方や患者の容態をきちんと確認する。患者の視野が広がるように、患者の足を進行方向に向けて移送する。

正解 1

- 感染性廃棄物に表示されるバイオハザードマークである。注射針やメス等の鋭利なものは黄色、血液等の付着した固形状のものは橙色、血液等の液状または泥状のものは赤色、と3種類の色で識別される。
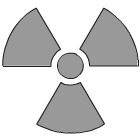
- 放射線が発生している場所で表示される放射能標識である。

- ヘリポートマークである。

- 禁止マークもしくは車両通行止めの標識である。
【問題19】 薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。
正解 2
- 身長
- 過敏症の有無
- 薬物の有害作用を予測するために、過去の薬剤による有害作用(副作用)やアレルギーの有無に関する情報を収集する。
- 1日水分摂取量
- 運動障害の有無
【問題20】 一般検査時の採血に最も用いられる静脈はどれか。
正解 4
- 上腕静脈
- 大腿静脈
- 大伏在静脈
- 肘正中皮静脈
- 一般的には肘正中皮静脈や橈側皮静脈、尺側皮静脈などが用いられる。安全に穿刺するため、皮膚からの距離が浅く、太くて弾力性があり蛇行していない血管を選択する。橈骨神経浅枝の損傷が起こる可能性があるため、手関節橈側での採血は避ける。
正解 2
- 携帯電話
- ライター
- 引火の危険があるため、火気の使用は厳禁である。
- 電動歯ブラシ
- 磁気ネックレス
【問題22】 創傷部位の創面の管理について正しいのはどれか。
正解 1
- 洗浄する。
- 創感染の予防をするため、創面を十分に生理食塩水等で洗浄する。細菌や壊死組織、滲出液などを除去し、創部および創部周囲を清潔に保つことは、創傷治癒の促進につながる。
- 加圧する。
- 圧迫すると創の循環不良につながり治癒を遅延させる。
- 乾燥させる。
- 良好な肉芽の形成には、清潔な湿潤環境が必要である。
- マッサージする。
- マッサージによって組織が破壊されると、治癒の遅延につながる。
【問題23】 高齢者の転倒による骨折が最も多い部位はどれか。
正解 5
- 頭蓋骨
- 肩甲骨
- 肋骨
- 尾骨
- 大腿骨
- 高齢者の転倒による骨折で最も多いのは、大腿骨頸部骨折である。治療が長引き、そのまま寝たきりになってしまうことが多い。高齢者に多い骨折には、大腿骨頸部骨折の他、橈骨遠位端骨折や腰椎圧迫骨折などがある。
正解 5
- 冠状動脈
- 冠状動脈は大動脈起始部から分岐する。
- 下大静脈
- 下大静脈を通った静脈血は右心房に流入する。
- 肺動脈
- 右心室から肺動脈に静脈血が送り出される。
- 肺静脈
- 肺静脈を通った動脈血は左心房に流入する。
- 大動脈
- 左心室は大動脈に血液を送り出す。
【問題25】 徒手筋力テストの判定基準は[ ]段階である。[ ]に入るのはどれか。
正解 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 徒手筋力テストは人体中の主要な筋力を判定する検査方法である。以下の6段階で評価する。
5 Normal(N)検査者が被検者の肢位持続力にほとんど抵抗できない
4 Good(G)段階5の抵抗に対して、被検者が抗しきれない
3 Fair(F)重力の抵抗だけに対して、運動範囲内を完全に動かせる
2 Poor(P)重力を取り去れば、運動範囲内を完全に動かせる
1 Trace(T)テスト筋の収縮が目で見て取れるか、または触知できる
0 Zero(活動なし)視察・触知によっても、筋の収縮が確認できない
- 徒手筋力テストは人体中の主要な筋力を判定する検査方法である。以下の6段階で評価する。